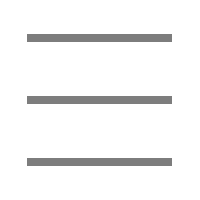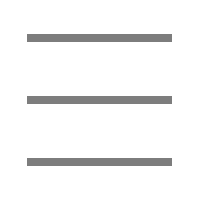三年B組、八坂金一。帝派の重鎮にして生徒会書記。十七歳とは到底思えぬ、中年のような老けた丸顔にだらしなく出っぱったビール腹、おまけに短足。おそらくは二、三十年前くらいの若者の間で流行していたアメリカの人気ミュージシャンを真似たようなパーマのかかった七三分けの長髪。帝派の大部分がそうであるように彼もまた金持ち家庭の〈上層〉で、ぼくらを〈下層〉と見下す嫌味な男である。眼鏡はかけていないが。しかし戦場では銃とナイフを駆使し、遠近攻守に隙のない戦いをする、帝派きっての実力者である。
「円藤縁人くんだね。谷垣主任がお呼びである。眼を醒ましたのであれば、今すぐ司令室まで来なさいとのことだ」
八坂はぼくにそう言った後、忍ちゃんの方に視線を向けた。一瞬、いやらしい笑みが彼の口元に浮かんだのを、ぼくは見逃さなかった。
「君もついでに来なさい。御菩薩池忍さん」
「は、はあ」
彼の眼に宿る光に不気味さを感じたのか、忍ちゃんの声から警戒している様子が伝わってきた。
八坂たちに連れられ、ぼくと忍ちゃんが保健室を出ようとし、
「あたしも行くぜ」
鈴子が八坂の眼の前に立ちふさがった。
先ほどまでへらへらしていた八坂の顔が急に曇り、唇を歪めて「ち」と舌うちした。
「君を呼んだ憶えはないのだが」
「呼ばれた憶えもねえよ。あたしの意志で勝手に行くんだよ」
鈴子が反論すると、八坂は露骨に鬱陶しそうに、しっしと鈴子を手で払うようにして言った。
「阿婆擦れの出る幕ではない。下層の雌犬は去れ」
「ああ? てめえ今なんつった」
鈴子が眉をつり上げて八坂に掴みかかると、どん、という鈍い衝撃音とともに、八坂の大きな拳が鈴子の腹に埋没していた。よく訓練された無駄のない、正確な打撃。
「ご」
鈴子が腹をおさえて短く呻くと、次の瞬間たてつづけに八坂の左フックが鈴子の右頬をとらえた。女子を相手にしているとは思えない、情け容赦の一切ない、怒涛の連続攻撃だった。
「やめろ!」
ぼくは間髪入れずに叫び八坂に食ってかかったが、背後にいた金縁眼鏡の男に頭を殴られ、逆に八坂に押さえこまれて地に伏す格好となった。ぼく程度の細腕ではびくともしない、圧倒的な力だった。すかさず八坂はホルスターから拳銃(愛用のベレッタ)を取り出し、ぼくのこめかみに突きつけた。
「おやおやあ。とうとう尻尾を出しましたか? 反乱軍スパイの円藤くうん。やむをえず射殺しちゃいますよ。ねえ、御菩薩池さん」
びく、と、八坂の背後から手刀を構えていた忍ちゃんが静止した。完全に気配を読まれているようだった。そして一瞬の隙を突かれ、彼女は〈金縁眼鏡〉によって首もとにナイフを突きつけられた。彼もまた、武闘派の猛者であるようだ。
「何やってるの!」
突然、女性の叫び声が聞こえてきた。振り向くとそこには、いつの間にか大型の自動拳銃を構えた江口先生が立っていた。
銃口は、ぼくを押さえつけている八坂に向けられていた。
「全員武器を捨てなさい。保健室での勝手なふるまいは、私が許しません」
江口先生の厳しい視線を受け、八坂は態度を一変させて貼りついたような愛想笑いを浮かべた。
「ははは。いやですねえー、先生。ちょっと戯れあっていただけですよ。ほら、おふざけもここまでにして、一緒に司令室に行こうか? 円藤くん、御菩薩池さん」
八坂が愛用のベレッタをホルスターに戻しぼくを解放すると、〈金縁眼鏡〉も忍ちゃんに向けていたナイフをしまった。鈴子は先ほど八坂にもらった二発が効いたのか、まだ床でうずくまっていた。完全に足にきていたようだった。無理もない、彼女は気性は男でも生物学的には女の子なのだ。
ぼくらはそのまま保健室を出、校舎の最上階にある司令室へと向かった。
道中、忍ちゃんが「きゃっ」と、小さい悲鳴をあげた。
「どうしたの?」
僕が訊ねると、忍ちゃんは「今、誰かが私のお尻を……」と、頬を赤らめて言った。恥じらう感じがとてもかわいらしく、あの〈人割り〉終零路と互角以上に戦える強さとのギャップも相まって、やはり忍ちゃんは素晴らしいということを再認識させられた。鈴子のやつなら恥じらうどころか拳が飛んでくるだろう。しかし、今はそれどころではない。
「だめだぞ、円藤くうん。いくら御菩薩池さんがかわいいからって、変な気を起こしたらだめだぞー。帝国軍人にあるまじきことだぞおー」
ぼくは名伏しがたい不快感に襲われた。このぶ男、ぼくに罪をなすりつけようとしてやがる。ぼくはやってないので犯人はおそらく眼の前のこいつだろう。忍ちゃんに悪い虫がつかないように、刮目して彼女を守っていかねばならない。エンド・セキュリティ発動。しかし今度はぼくの視線が気になったのか、忍ちゃんが「な、なんですか? 縁人先輩」と、さらに困惑した様子を見せた。ああ、もう! 本当にかわいいな、この娘は!
そんなことを考えていたら、司令室のぶ厚い装飾つきの豪奢な扉が、すでに眼前まで迫っていた。
八坂が扉をノックした。「八坂です。円藤縁人と御菩薩池忍を連れてまいりました」
中から「よろしい。入りなさい」という谷垣らしい人物の声が聞こえ、ぼくらはそのまま中へ入った。上層の連中や貢献度の高い生徒ならともかく、ぼくらのような下っ端が司令部に呼び出されるのは大抵ろくな用事じゃない。無茶な任務を押しつけられるか、失態を責められるかのどちらかであることが多い。夢葉奪還作戦に任命された時はその両方だったが、スパイ疑惑がかかっている今は一体何を言われるのやら……
以前と同じく三人分ほどある高そうな木製の机の中央に、二年の学年主任・谷垣、その右には射撃訓練教官の根津が座っていた。左側は空席だった。
「ふん。よくもまあぬけぬけと司令室に顔出しができるものだな。え」谷垣が毒づいた。
「ご期待に添えず、申しわけありません」とりあえず、ぼくは頭を下げて任務の失敗を詫びておいた。忍ちゃんも追従して頭を下げた。
「一度ならず二度までも、貴様らはわれわれ司令部の、ひいては軍の期待を裏切ったわけだ。……が、まあいい。今は置いといてやる。今日は説教をするために呼んだわけではない。もっと重要なことだ。わかるかね」
スパイ疑惑のことか、と、ぼくは思ったが、顔には出すまいと平静を装って「いいえ」と否定した。
「君にかけられている、スパイ容疑についてだよ」
谷垣がやや高圧的な声で言った。
「スパイはぼくじゃありません。下北沢です」
本当のことなのでぼくは堂々と否定した。堂々としすぎていたのか、谷垣の眉がぴくりと動いた。
忍ちゃんが続いて言った。
「羽柴さんも共犯でした。先ほども申し上げたとおりです。彼は任務中に突然私に斬りかかってきました。酉野先生がかばってくれなかったら、今ごろ私はここにはいなかったでしょう」
根津がぼくらを無視して喋りはじめた。「彼らは日出川の地下水路で死体で発見されたよ。かわいそうに。下北沢くんは顔をつぶされていた。君ら臆病者とは違い、彼らの忠誠は本物だった。彼らは夢葉嬢を助けだすため、名誉の殉職を、えふっ」なぜか途中から半べそになっていた。わけがわからなかったが、そういえば彼は羽柴のクラスの担任か。教え子が死んで悲しいのかな。根津はもともと坊ちゃん刈りの童顔だから、小学校の頃ガキ大将にいつもいじめられて泣いていたクラスメイトみたいで、ぼくはこみあげてくる笑いを我慢するのに必死だった。忍ちゃんは根津の予想外すぎるアクションにどう反応したらいいのかわからずにとまどっている様子だった。
「彼らこそ真の軍人、おおおん、あーんあん」
とうとう号泣しはじめ、ぼくの腹筋はもう限界寸前だった。もしかしてこれは任務失敗の罰か何かなのだろうか。
「あす……水無月先輩も、〈首刈り〉との交戦中に下北沢に襲撃されて重傷を負いました。ぼくも殺されかけました。けれど、すんでのところで酉野先生が助けてくれました。下北沢の死体をよく調べれば、彼が誰に殺されたのかわかるはずです」
谷垣が意地悪そうに眉をひそめた。「君らが、彼らに罪をなすりつけようとしているのではないかね? たとえば酉野くんの死体から武器を奪い、下北沢くん殺害後に偽装したという可能性もある」
「ちがいます。濡れ衣です。下北沢自ら暴露しました。羽柴もグルです」
「暴露しました、では何の証拠にもならんよ。第一、彼らが軍を裏切っていったい何のメリットがあるというのかね」
「彼らは夢葉の親衛隊です。夢葉を反乱軍に売り渡し、自分たちも寝返って独占しようとしてました」
本当は羽柴はこっちに戻ってきてぼくがスパイであることを証言するつもりだったようだけど、ややこしいので省いた。これが羽柴の取り調べだったら、おそらく彼らは羽柴の言うことを鵜呑みにするのだろう。証拠も下北沢が捏造したと言っていた。彼らにとって重要なのは、都合の悪い真実よりも都合のいい嘘なのだ。
「馬鹿馬鹿しい!」
谷垣が拳縋で机をがんと叩き、怒鳴った。突然大きな音を立てられ、ぼくの心拍は急上昇した。
「妄言も休み休み言いたまえ。できの悪い戦争映画じゃあるまいし、そんな色恋沙汰で軍を裏切り、味方を殺すなどということがあってたまるか。君が反乱軍から高額の報酬と引きかえに情報を売り渡したのではないかね。君の家はたいそう貧乏だそうじゃないか。え。そもそも君たちは任務へ赴く前に、私に何と言った」
不愉快極まりなかったが、ぼくは何も言い返せなかった。強要されたとはいえ、「学園と国に自分の身を捧げる」と言ってしまったのだから。
「白虎学園、校訓第二条!」谷垣が叫んだ。
「お国のために、軍のために、学園のために、その身を捧げ、不屈の精神で最後まで臆することなく戦い抜くこと」
ぼくと忍ちゃんは同時に唱和した。理不尽さによる怒りで声がわなわなと震えているのがわかった。
「声が小さいぞ!」谷垣の怒声が部屋に響きわたった。
「お国のために、軍のために、学園のために、その身を捧げ、不屈の精神で最後まで臆することなく戦い抜くこと!」
ぼくは投げやり気味に叫んだ。
「そうだ! 貴様らは出発前に改めてそう誓ったではないか! それを夢葉嬢の奪還に失敗した挙句! 一度ならず二度までも! 生き恥をさらしおめおめと逃げ帰るとは何ごとか! 貴様は嘘つきか! このっ!」
谷垣の拳が、ぼくの右頬を捉えた。先日の任務で切れた口の中の傷がふたたび裂け、口の中を鉄の味が満たしていくのを感じた。
怒りで鼻息を荒らげ、谷垣は続けた。
「弁明のひとつも出ないのか。さすがはあの馬鹿女の教え子だな」
その言葉を聞いた瞬間、ぼくは頭にすさまじい勢いで血が昇っていくのをはっきりと認識した。
「やつの班は、以前から任務の成功率がぱっとしない割に隊員の生還率が高かった。無能の上に臆病な、下層出の士官にありがちなクズ。あの教師にしてこの教え子ありか。この、下層のできそこないの、下郎ども」
ぼくの中で、何かが音を立てて切れた。
ごん。
谷垣の左頬に、いつの間にかぼくの右拳がめりこんでいた。
彼は盛大にふっとび、豪奢な机に背中から思いきり叩きつけられ、仰臥位で寝そべる形となった。
そのままぼくは止まらず、何かに駆られたように寝そべった谷垣に飛びかかり、馬乗りになって手のひらに爪が食いこむほど強く握りしめた拳を、振りあげた。
「縁人先輩。すいません」
背後から誰かの声がした。
直後、首の後ろに強い衝撃を感じ、ぼくの視界はブラックアウトした。