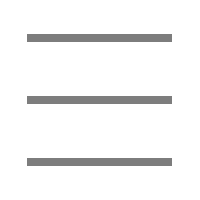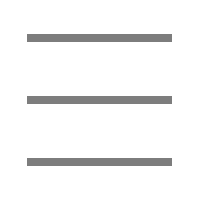一九九九年七月、ロシア某所。
旧ソ連時代は核開発秘密都市アルザマス17と呼ばれたゴーストタウンから数キロ離れた黒海沿岸のあるところに、巨大な廃棄物処分場があった。
そこでロシア秘密諜報部隊所属のイワノフとサーシャは、誰もいない深夜に密かにゴミ漁りをしていた。
ロボットのようにひとり黙々と目的のものを探し続けるサーシャに、半ば投げやりな態度でイワノフが訊ねる。
「おい。本当にあるのか。世界滅亡爆弾なんてのは」
「上があるというんだから、あるんでしょう。私たちはただ命令に従い、標的を見つけて無力化するだけですよ。いいから手を動かしてください、先輩。隊長にチクりますよ」
抑揚に欠けたどこか無機質な声で、サーシャは黙々と捜索を続けながら、先輩を詰った。
世界滅亡爆弾――ソビエト連邦時代に〈特殊兵器部門〉が密かに開発を進めていたという、最悪の兵器。
一九六一年、ソ連は人類史上最悪の水爆ツァーリ・ボンバを完成させ、自国の領土で実験。
その強烈な破壊力は、ヒロシマに投下された原爆の三千三百倍以上。
発生した五十メガトンの衝撃波は、地球を三周し。
周囲数十キロメートルにあるすべてを焼き尽くし。
千キロ以上離れた地にまで、死の灰を送り届けたといわれている。
だが時代の変化とともに核兵器開発は破壊力よりも小型化に重点が置かれるようになり、ミサイルや無人機に搭載して命中精度をあげ、いかに敵国の重要拠点をピンポイントで無力化するかを、各国が競うように開発していた。
一九九九年七月に恐怖の大王が現れ、人類を滅ぼすというノストラダムスの大予言を、憶えているだろうか。
実際に信じていたのは一部の狂信者のみであり、政府関係者はおろか大衆の大部分が虚構だと断じていた。
しかし――
実はこの予言を実現すべく、ツァーリ・ボンバをはるかに凌ぐ超威力の核兵器を開発している者がいた、という事実が後になって発覚したのだ。
フリストフォル・バクシン博士。ソ連水爆の父とも呼ばれたアンドレイ・サハロフ博士の教え子であり、人類抹殺を標榜する秘密結社ヘリオスのメンバーだった男。
この団体は、世界を地獄の業火に叩きこみ。
自分たちとその従者、彼らの利益を守る警察と兵士、そして従順な少数の大衆だけは宇宙に逃れ。
地上に残った全人類を抹殺するという、終末計画を掲げており。
世界の大部分の富を独占する富豪一族の資金援助を受け。
ツァーリ・ボンバを超える世界滅亡爆弾の開発を、密かに続けていたという。
結局バクシン博士はその最凶兵器が完成する前に、ソ連共産党によって粛清された……はずだったのだが。
実は、すでに世界滅亡爆弾は完成し、一九九九年七月に作動するよう仕掛けられていたという。
バクシンの遺書に書かれていたというその言葉を、ロシア政府の上層部は発狂したバクシンがイタチの最後っ屁に書いた虚報だと一蹴したのであるが。
いざ一九九九年七月が近づくにつれて「万にひとつという事態もありうる」と、秘密諜報機関の総力をあげて調査し。
つい先日、世界滅亡爆弾がこの巨大廃棄物処分場に隠されているという極秘情報を、掴んだのだ。
* * *
「おい。そんな冷蔵庫の中にあるわけないだろう」
呆れ声で言うイワノフに。
「ありましたよ」
真顔でサーシャは返答した。
「だろ? 全人類を抹殺できる最凶兵器が、そんな冷蔵庫に格納できるわけ――って、ええ!?」
あまりに予想外の返答に、イワノフは開いた口が塞がらなかった。
「設計図通りの形ですね。思っていたより小さいですが、まあ稀代の天才と呼ばれたバクシン博士のことですから、驚くほどでもないでしょう」
相変わらずアンドロイドの如き無表情のまま、サーシャは述べる。
「危ないところでした。爆発まであと四十五秒でしたよ。先輩」
そう。世界滅亡爆弾は時限式だった。
その正確な起爆時刻は謎のままだったが、液晶の時計を見るにちょうど今日の午前四時四十四分四十四秒に爆発するよう、セットされていたようだ。
「先輩。〈例の装置〉を」
「ああ」
例の装置とは、最近ロシアが極秘裏に開発したという、核分裂反応を無効化する特殊な装置のことである。
イワノフは腰に下げられたホルスターから、先端にゴルフボールほどの金属球がついた拳銃のような装置を取り出し、サーシャに手渡した。
そしてふと、上司に聞いた話を思い出す。
曰く――この装置を開発したのは、バクシン博士ではない。
世界を滅亡させるための時限爆弾に、そんなものを仕掛ける意味がないからだ。
稀代の天才バクシン博士にはロトキンという助手がおり、彼が手掛けた物だという。
だが非凡なバクシンと比べ平凡だった彼はことごとく失敗作を量産、危うく研究所をクビにされる寸前だったらしい。
バクシンのたったひとりの助手ということで、〈例の装置〉開発プロジェクトのリーダーを任されたそうなのだが。
そんなやつの開発した装置が、稀代の天才科学者の作った世界滅亡爆弾を、本当に無効化できるのだろうか……?
最悪、爆弾の無効化に失敗してその場で爆発――人類滅亡。
そんな可能性が、イワノフの脳裏を過る。
ならば――
「待て、サーシャ」
何かを決意したイワノフは、サーシャが爆弾を無効化する前に、言葉を紡ぎ出す。
「俺たち、もしかしたらここで死ぬかもしれない」
「そうですね。元より機関に入った時から、殉職は覚悟の上です」
サーシャの返事は、そっけない。
「俺もそうさ。でもな……」
イワノフは、サーシャの顎を引き寄せ――その唇に接吻をした。
サーシャは、特に抵抗するそぶりを見せなかった。
「どうしたんですか。いきなり」
ただイワノフの行動が予想外だったのか、わずかに眼を見開いた。
「最初に会った時から、お前のことが好きだった。死ぬかもしれないから、その前に気持ちを伝えておきたかったんだ」
「……そう、ですか」
サーシャの表情は、微塵も揺るがない。
氷の諜報員と呼ばれた、いつものサーシャだ。
「私には……よくわかりません」
サーシャは、〈孤児院〉の出だ。
「恋とは、どんなものなんでしょう」
ただの孤児院ではない。機関の諜報員を幼少の頃から育てあげるための、秘密養成所だ。
物心ついた時から地獄のような訓練と勉強漬けの毎日を送り、今の今まで色恋など知る機会もなかったのだろう。
「それは、これから知っていけばいいさ」
イワノフは、力なく笑う。
今はあえて、返事は聞かない。
この任務を無事に終えることができたら、また後日改めて休暇でもとって、サーシャをドライブに誘って、その時にまた聞こう。
「んじゃ、爆弾を無効化しようか」
液晶の表示は、残り十五秒。
上司の話では、例の装置の先端を爆弾に接触させて青いボタンをひと押しするだけ。
たったそれだけのことで、この最凶の爆弾は一瞬で無効化されるという。
「ええ。では早速」
サーシャが無表情のまま、しかしどこかポカンと間の抜けたような顔で。
「――って、あれっ。装置はどこに?」
空の両手を、見つめていた。
イワノフは眼を大きく見開き――硬直する。
そして即時に任務よりも己の願望などを優先してしまったその浅薄さを、呪った。
「あっ。くそ。どこだ。あっ。どこだよ畜生」
恋愛などまったく知らぬサーシャにあんなことをして、彼女が動揺せぬはずがなかった。
訓練で叩きこまれた無表情の、その下で。
サーシャは例の装置をうっかり落としてしまうほどに、取り乱していたのである――
爆弾の秒読みは、残り五秒。
血眼になって周囲を見渡し、例の装置を探す二人。
イワノフが、ふとサーシャの背後に眼をやると――
小汚い野犬が、例の装置を咥え、遠くに走り去っていく――!
「ま、待って――」
サーシャは無表情のまま冷や汗をかき、全力で野犬を追った。
――しかし。すべてが手遅れだった。
爆弾の秒読みは、すでにゼロ秒。
瞬時――二人の視界が、白飛びし。
史上最強のツァーリ・ボンバの――実に数百倍もの大きさの〈第二の太陽〉が。
恐竜をも絶滅させた巨大隕石の衝突を想起させる超巨大爆発を引き起こし。
地球上の全人類を、抹殺した。