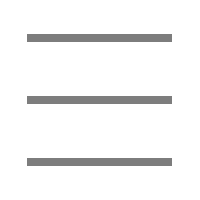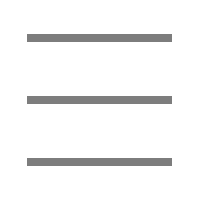「ハア~。誰だよ日本にハロウィンなんて持ちこんだヴァカは。おかげでこちとら今日も残業だよ!」
おれの名は斜竹太郎。都内某所の古びたオフィスビル内にある零細企業で働く若きSE(社会人二年め)だ。
今日こそは定時で帰り、同棲中の彼女とイチャイチャする予定だったのに、どこかのパリピが導入したハロウィンなんてわけのわからんクソイベントのおかげで上司の田抜にシステムトラブルの原因究明なるめんどくさい仕事を押しつけられ、激務に喘いでいた。
その田抜は「ハロウィンだから息子にプレゼントを買って帰らねばならぬ」と、おれにすべて丸投げしてさっさと帰りやがった。
あの野郎、何が「君は独身だから、暇だろう?」だ。
余計な詮索されたくないから独り暮らしの無趣味人間を装ってるだけで、こっちにも大事なプライベートの用事があるんだよ!
――なぜこんな理不尽がまかり通っているのかといえば、我が社は実力主義とは程遠い縁故主義がまかり通っており、あの上司は世渡り上手で部長や役員、ひいては社長ともナアナアな関係で、下手に逆らえばヤツの鶴のひと声でリストラ予備軍に追いやられたり、地方への転勤を強いられたりなど制裁人事が待っているからだ。
しかしSEとしては社内でも一、二を争うほど仕事の早いおれは、さっさと業務を片づけて夜の七時半には退勤することに成功する。
* * *
「ちっ。雨か」
十月三十一日ともなれば日没時間も早まり、空はすっかり暗くなっていた。
その黒い空から舞い落ちる小雨が、地平の彼方まで続く無数のネオンに照らされて虹色に輝き幻想的な雰囲気を醸し出していたのだが、激務で疲れ果てた社畜にはもはやどうでもよく。
さっさと家に帰って恋人とスウィートなひと時を過ごすべく、駅まで全力疾走する。
「おい。おっさん。約束の金は用意したのかって聞いてんだよ」
駅の近くの路地裏から、若い女の声が聴こえてきた。
こっそり壁の裏から覗きこんでみると、そこにはふたつの人影。
「あれは……」
ひとりは知らない制服姿の女。
もうひとりは……何とあの田抜だ。
あの野郎、子供にプレゼントを買うために早く帰ったんじゃなかったのか?
うまくいけばヤツの弱みを握れるかもしれない、と、おれはしばらく物陰から様子を見ることにした。
「金はこないだ渡しただろう。まだこれ以上俺をゆするつもりなのか」
田抜が蚊の鳴くような声で言った。
「うるせえ! 仮にも会社の役員なら五万ぐれーポォンと出せるだろ! ないならさっさとATMで下ろして来いよ。奥さんに写真送りつけるぞ」
女は眼をつりあげ、そのへんに転がっていたポリバケツを思いきり蹴りつけて田抜を威嚇した。
髪は金髪、スカートは短く、ブラウスの胸元は第二ボタンまで外されて大きくはだけている。典型的な不良女子高生だ。
おそらく以前に田抜に援交を持ちかけ、しかし情事を写真に収め、それをネタに恐喝しているのだろう。
いい気味だ、馬鹿め。
おれは邪悪な笑みを浮かべて状況を見守った。
このネタをチラつかせれば、ヤツも今後おれには大きく出られまい。
名も知らぬ女子高生、GJ!
「ううう。うーうー」
田抜がいきなり駄々っ子の三歳児のように呻き、土下座しだした。
「こここ、こう見えてもおれ小遣い月三万しかもらえてないンだよオ~。せめて次の給料まで待ってくれよオ~」
「ぶふッ」
田抜のなりふり構わぬあまりにみっともないその態度に、おれはこみあげる笑いをこらえるのに必死だった。
だめだ……まだ笑うな。こらえるんだ……
田抜の懇願を受けて、しかし女子高生は、さらにつけあがり。
「はア――!? オメー、先月もンなこと言って逃げてたじゃねーかよ! こっちは金が要るんだよ! これ以上は絶対待たねーからな! ホラ、奥さんにRHINEで送っちゃうゾ~?」
スマホの画面をまざまざと見せつけ、脅迫する。ちなみにRHINEとはドイツ発祥のSNSで、アドレス帳のデータを使って見知らぬ人を勝手にフレンド登録する迷惑仕様で有名だ。おそらくこの機能を利用して女子高生は田抜の奥さんの連絡先を入手したのだろう。なお名前の由来は言うまでもなくドイツのライン川。
「や、やめろオ――!!」
それは、完全に勝利を確信していた女子高生の不意を突いた――
――土下座からの、急襲だった。
眼の前でみっともなく醜態を晒している情けない男が、いきなり自分めがけてタックルしてくるとはさすがに予想外だったのか、女子高生は田抜に押し倒され、ヤツもろとも濡れた地面の上に倒れこんだ。
女子高生の差していた傘とスマホが派手に地に落下し、こちらへと転がりこむ。
「テメエ調子に乗んなヨ」
田抜は女子高生の口をその手で塞ぎ、先ほどまでとは態度を百八十度変え、チンピラ・ヤクザのごとく凄んでみせ。
「その顔に一生消えねえ傷でもつけてやろうかオイ」
ポケットから十徳ナイフをとりだし、刃渡り三センチくらいの短いナイフを出して、チラチラと見せつけた。そういやヤツはアウトドア趣味だったな、などとおれは能天気にもそんなことを思い出す。
「んんんんん」
女子高生は必死で叫ぼうとするが、口を塞がれていては大きな声が出せない。
しかもここは人気のない路地裏。
助けが来る可能性は限りなく低いだろう。
ここで田抜が女子高生を脅して写真を消去させたりスマホを破壊されたら、すべてが台無しだ。
仕方ない……
「ふっふ~。そこまでですよ。田抜先輩」
意を決して、おれは〈仲裁〉に入ることにした。
「しゃ、斜竹君。何でここに……? し、仕事のはずじゃ」
田抜の眼が、まるで幽霊でも見るかのごとく驚愕に見開かれる。
「仕事なら終わらせましたよ。息子さんにプレゼント買って帰るんじゃなかったんですかね。おれに仕事押しつけて」
嫌味たっぷりにそう言うおれの手には、すでに女子高生のスマホがあった。
その画面には彼女と田抜がベッドで情事に耽っている写真がすでに表示されており、田抜の奥さん宛に送信ボタンひとつで送れるようスタンバイされている。
あとはスマホの画面をおれがほんのひと撫でするだけで、田抜の悪事はすべて奥さんにバレ、秒で家庭は崩壊、ヤツは今後延々と慰謝料と養育費を払い続けるATMと化すであろう!
おれの手にあるスマホを見て、田抜の顔色が青ざめる。
「――斜竹君。私はその、彼女に脅されて、仕方なく……だな。今流行りの、オヤジ狩りってやつだ。わかるかね。私は被害者なんだよ。だからちょっと、彼女に……教育的指導を、だね……」
しどろもどろになりながら、持ち前の話術で必死に考えながら言い訳を紡ぐ田抜に。
しかしおれは、スマホの画面に映されている情事の写真を、満面の笑みでまざまざと、見せつけた。
「援交は犯罪ですヨォ? あとこれ、奥さんのアドレスですよね」
すべてが筒抜けだったと悟った田抜は硬直し、やがて媚びるようなキモチの悪い上目遣いで、おれを見つめてきた。
「わ、わかった。斜竹君。私が悪かった。今まで君を冷遇してきたこと、心から詫びるよ。君がうまく昇進できるよう、私の方から部長に取り計らってやろう。残業も今後一切なしだ。だから、その、写真を」
「とりあえず、その娘を――」
田抜の〈取引〉を遮り、おれは義憤に駆られて女子高生の身柄の解放を要求しようとして――言葉を止めた。
バカが。正義のヒーローのつもりか。
ここで女に騒がれたら、田抜のやつをいじめて楽しむこともできない。
「他には? おれ、別に出世とか興味ないんで」
淡白な態度で突き放すおれに、田抜は必死で縋り続ける。
「じゃ、じゃあ金か? わ、わかった。次のボーナスの査定を最高にするように、私の方から人事課に働きかけて――」
「ノンノン。おれ無趣味なんで。酒も煙草もやらんし、車とかも興味ないし」
「なら、何が望みだ? な、何でも言ってくれ。お、女か? そ、そうだ。君はまだ独身だったなっ。それなら庶務課の橋友君を――」
橋友神奈。会社一の美女と名高い庶務課の花だ。しかし――
「あー。実はおれ恋人いるんですよ。隠しててサーセン☆」
おれがあくまで上司いじめを愉しんでいるだけだと悟ったのか、ヤツの顔に張りついていた気持ち悪い愛想笑いが、徐々に消えていく。
このまま女子高生のスマホを没収するか、あるいはブルートゥース送信でおれのスマホに写真を送るなどして田抜の弱みを握り、会社内でおいしい想いをするのも悪くはない。が――
ここでこの写真を送信してやる以上の楽しみが、果たしてあるだろうか?
おれは悪魔さながらにほくそ笑み、あえて送信ボタンを――押した。
一瞬の後、「送信完了」という死刑宣告を突きつけられた上司は。
「アアアアアアアアウワアアアアアアアウアウア――!!」
まるでムンクの如き形相で、もはや人眼もはばからず、壊れたように叫んだ。
「ヒャーッハッハッハァ! これでテメエは一巻の終わりだナァー!」
溜まりに溜まった鬱憤を、最高の形で晴らせたおれは。
あまりの解放感に耐えきれず、狂ったように哄笑していた。
きっとその顔は今の田抜には悪魔……いやその頂点たる魔王のように見えていたにちがいない。
田抜のヤツ、怒り狂って十徳ナイフで切りつけてくるかな。
――などと、おれは警戒したが、ヤツは隙を突かれて女子高生に金玉を蹴りあげられ、それは杞憂に終わった。
彼女にスマホの返還を求められたおれは、爽やかな笑顔でそれに応じる。
田抜の人生はすでに破壊した。もうスマホにも女にも用はない。
「あんたのせいで、全部台無し。ざっけんなよ」
これ以上たかることができなくなった、と、彼女はそれだけ言って中指を立て、夜の町へと消えていった。
せっかく田抜に隙を作って逃してやったのだから、礼のひとつくらい言ってほしかったのだが、まあどうでもいい。
「斜竹テメェ……俺の人生メチャクチャにしといて、タダで済むと思うなヨ……?」
田抜が怨嗟をこめてそう言った。
「あ~。関係ないね。おれ、もう会社やめるんで」
こうなれば上司が社内人事でおれに復讐してくることは間違いない。
どのみち遠くないうちに馘首になるし、正直待遇にも不満はあったので、明日にでも辞表を突きつけてやろう!
おれほどのスキルがあれば、人手不足が叫ばれる中、IT職などいくらでも見つかる。
そんなことより、今はおれの私生活をことごとく踏みにじってきた宿敵に天誅を下すことができて、最高に嬉しい。
人生でこれほどまでに高揚した瞬間が、かつてあっただろうか? いや、ない(反語)。
路地裏で股間を押さえながら無様に横たわる田抜に、先ほどの女子高生と同じように中指をおっ立て、おれは駅へと向かった。
少し遅めに帰宅したおれを、恋人の花子はおいしいビーフ・シチューで迎えてくれた。
今日の話を肴に、おれたちは今までの人生で最も美味い酒を呷り。
その後、メチャクチャイチャイチャした。