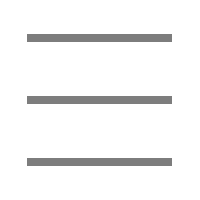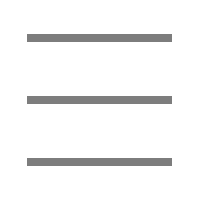今は昔。はるか西の彼方にある大国、マスカール帝国の、その玉座の間。
豪奢な黄金の玉座に、ひとりの高貴な装いの女性が、尊大に足を組んでいた。
彼女の名は、エリザベート。
当時のこの地域においては珍しい女性の君主であったが、政治、外交、そして戦の指揮官としても極めて有能であり、最強の軍隊を率いて連戦連勝、次々と周辺国を侵略、占領し、歴史的にも類をみない稀代の名将であった。
だが生まれてこの方、空前の才覚でもって挫折を知らずに育ってきたその性格は高慢傲慢驕慢暴慢傲岸不遜大胆不敵であり、民から重税をとりたてて贅の限りを尽くし、国内からはおろか、城内からも不満の声があがりつつあった。
「我が君。民の暮らしはもはや限界でございます。これ以上年貢を増やしては国内を不況のどん底に叩き落し、反乱が起こるのも時間の問題かと――」
エリザベートの騎士にして帝国最強の騎士と名高いフランシスは、己の君主にそう諫言する。
「うるさいのう」
エリザベートは玉座から立ちあがると、爬虫類が如き冷たい眼光で跪くフランシスを見おろし、威圧的に歩み寄り――
彼の頭を、その細いヒールで思いきり踏みつけた。
「がぁ」
いくら王国最強の騎士とはいえ、尖ったヒールで体重を乗せて踏みつけられ、石の床に頭を叩きつけられればダメージを受ける。
「そなたはただ黙って妾の命令に従う人形であればよいのじゃ。妾の政策に口出しをするとは、偉くなったものよのう?」
ヒールの先でグリグリと抉るようにして、フランシスの後頭部を蹂躙する。
その氷の瞳には部下に対する思いやりや労りといった感情は、一切感じられない。
あくまで圧倒的な能力と、民を跪かせる天性のカリスマをもって君臨する暴君であり、部下に慕われるというよりは恐怖で支配しているのが現状だ。
「も、申しわけありません。あっ。出過ぎた真似を。あっ。あっ。ど、どうかお許しを」
延髄をキリキリと踏みつけられ、地獄の激痛を与えられるフランシスは、悲鳴をあげて己が君に許しを乞う。
「いいや。タダでは許さぬ。このエリザベートに逆らった者には、たとえ直近の騎士であろうと罰を下さねばのう。うっひっひ」
悪魔のように嗜虐的な笑みを浮かべ、フランシスを痛めつけるエリザベートのその姿は、まるで部下いじめを楽しむパワハラ上司の如し。
「ええい、そうじゃ。鎧を脱げ。服を脱いで裸になるのじゃ、フランシス」
「し、しかし。そんなことをしたら、いざ刺客が襲いかかってきた時に御身をお守りすることが困難に」
口答えは、火に油。
「わらわがそのへんの有象無象に遅れをとるとでも思っているのか! いいからさっさと脱がんか! このまま頭を踏み砕かれたいか」
そう、国内外に敵の多いエリザベートを暗殺せんと試みた者は、枚挙にいとまがない。
今まで刺客たちはその都度最強騎士フランシスの剣の錆となっていったのだが、敵は二十四時間三百六十五日、いつ襲いかかってくるかわからない。
かつて一度だけ、エリザベートが入浴しているところを女中のひとりになりすました刺客が襲いかかったことがあった。
――が、幼い頃から先王に地獄の訓練で鍛えられていたエリザベートは、華麗な上段後ろ回し蹴りで刺客の頭蓋骨をあっさり粉砕してしまったのだ。
エリザベートの強気は、単なる虚勢ではない。
「ああ! これ! パンツまで脱ぐでない、このたわけ者! 投稿サイトの規定に引っかかるであろうが」
聡明なるエリザベートは、フランシスがパンツを下ろしてしまう寸前で制止する。
当然だ。そんなことをすれば作者は規約違反でアカウントを凍結されてしまう。
パンツ一丁になった己が下僕に、エリザベートは興奮し、舌なめずりする。
何せフランシスはかなりのイケメンだ。
「よおし。次は地べたに四つん這いになるのじゃ。犬畜生のようにのう」
意地悪く嗤い、エリザベートはフランシスにそう命じる。
「それは」
フランシスは躊躇した。
彼も由緒正しき名家の生まれだ。
周囲に参謀や女中もいるのに、そんなみっともない真似をしろというのか……
いや、それこそがエリザベートの本当の狙いなのだろう。
フランシスに恥をかかせて楽しんでいる。羞恥プレイだ。
「早くせぬか、愚図!」
エリザベートは足を高く振りあげ、ふたたびフランシスの頭を踏みつけ、フランシスは不本意ながら這いつくばる犬畜生の格好となった。
女中たちの視線は騎士をあざ笑うものではなく――むしろ憐れむものであったが、しかし誇り高き武人のフランシスにとっては、それが何よりも耐えがたい恥辱だった。
「そなたらもよく見ておくが良いぞ。妾に逆らう者がどうなるかをのう」
フランシスのラクルテル家は、代々マスカール皇家に仕えてきた由緒正しき家系だ。
最初に仕えたのはエリザベートの父、すなわち先王であるが、フランシスが騎士となってから半年後に急性胃腸炎で急死。
以降、エリザベートがフランシスの新しい主人となったのである。
先王はエリザベートとは違い、民を想い帝国の発展を願う王の中の王であり、その求心力は高く、民からも臣下からも慕われる名君であった。
フランシスは、そんな王のためなら喜んで盾となって死ぬ覚悟があった。
そして偉大なる先王の娘ならば、たとえ今は傲慢であろうと、いつの日か改心し、国を良い方向へと導いてくれるだろう、と、期待していた。
――だがエリザベートが王座についてからの十年間、その増上慢は改まるどころかますます磨きがかかっていく一方であった。
* * *
結局数時間もねちっこくいじめられたフランシスは身も心も疲弊し、自身の部屋の寝台に倒れこむように横たわった。
夜に飲みこまれるかの如く暗転する彼の意識は、しかし突然何者かが扉をノックしたことで、ふたたび覚醒する。
……誰だ、こんな時間に。
今は夜の十時すぎ。
女中たちも仕事を終えて寝る時間だ。
「誰だ」
扉を開けると、そこにいたのは女中のエレーヌだった。
平民の出でありながら人一倍熱心に働く、女中の中でもなかなか好印象の若い女。顔もいい。
「あの。フランシス様」
「エレーヌか。どうしたのだ」
「ちょっとお話が」
キョロキョロと周囲を見渡すエレーヌは、あからさまに挙動不審であった。
「話なら、ここで聞こう」
騎士ゆえの性質か、嘘や内緒話を嫌うフランシスは、決して小さくない声で、そう言う。
しかし――
「エリザベート様のことで、お話がございます。大切なお話です」
「何だと」
フランシスの顔が、曇る。
「周囲に聞かれると、あなた様も私も困ります。お部屋の中で、ふたりきりでお話しとうございます」
フランシスは数瞬迷った。
エレーヌの震える全身が、ただごとではないと物語っていたからだ。
何か重大な情報を握っている、と。
エリザベートに対する忠誠心が本物ならば、その尊き身に迫る如何なる脅威も、排除しなければならない!
この期に及んで、たとえ臣下の前で犬畜生同様の辱めを受けてなお、フランシスの忠誠心は本物だった。
それはエリザベートの天才的な王としての資質ゆえか、それとも彼の遺伝子に刻みこまれた騎士としての本能がそうさせたのかは、本人にもわからない。
「わかった。いいだろう」
意を決したフランシスは、エレーヌを部屋の中へと招き入れる。
絢爛豪華なエリザベートの寝室や謁見の間とは対極的に、病的なまでに質素で武骨なフランシスの部屋。
寝台の上に座るフランシスに、跪くようにして。
エレーヌは、口を開いた。
「先王様の死因は、病死ではございません。エリザベート様が、医師に命じて毒殺させました」
「何だと貴様!」
エレーヌの言葉にフランシスは激昂し、彼女の胸倉を片手でつかみ、軽々と持ちあげた。
「我が君を愚弄する気かァ!」
怒りに我を忘れるフランシスに、しかしエレーヌは抵抗することなく。
逆に――その身を委ねるように、力を抜いた。
エレーヌの異変に気づいたフランシスは、とりあえず彼女が窒息する前に、乱暴に地面に投げ落とす。
そして寝台の脇に置いてあった剣を素早く抜き、エレーヌの喉元に、突きつける。
だが彼女が逃げ出す様子はない。
「なぜ逃げない」
今にもエレーヌを斬り殺しそうになる自分を必死で押さえながら、フランシスは問う。
「真実だからでございます。私はエリザベート様が先王様お抱えの医師を口封じに殺すところを、目撃しました。今まで恐ろしくて誰にも言えなかったのですが――もう我慢の限界でございます」
体は震えていたものの、エレーヌはフランシスの眼をまっすぐに見据え、はっきりと、そう言った。
今にも殺されかけているというのに、あまりにも堂々とした――そう、死の覚悟すら感じさせる、エレーヌの不動の態度に。
フランシスは明らかに、気圧されていた。
一介の女中風情が、嘘でここまでできるだろうか?
そんな疑念が、脳裏をよぎり。
「その話に嘘偽りはないと、神に誓うか」
フランシスは鋭い視線で、エレーヌを詰問する。
「誓います」
エレーヌの瞳に、迷いは感じられない。
彼女が見たという〈秘密〉はあくまで証言のみであり、エリザベートを糾弾するには不十分である。
しかし動機としては充分すぎる上に、フランシスが抱いていた一抹の疑念――あの偉大な先王が急性胃腸炎で死んだなどという馬鹿げた話の真相としては、もっとも自然かつ真実に近い仮説。
フランシスは、ある決意を固める。
「もしその言葉が嘘だとわかったら、私はお前を許さない」
あまりの剣幕に、エレーヌは一瞬びくりと体を震わせたが、すぐにフランシスの眼を見て、口を開く。
「はい。――覚悟は、できております」
その決意はどう見ても本物であり、嘘をついているようには到底思えない。
* * *
「話とは何じゃ。フランシス」
翌日の謁見の間、玉座の下で跪くフランシスを、エリザベートの鋭い眼光が見おろしていた。
どことなく雰囲気のおかしなフランシスの様子に、エリザベートの口調もいつも以上にトゲトゲしかった。
フランシスはどこか据わった眼でエリザベートを見あげ、口を開く。
「貴女様が先王様を殺した、という話をある者から聞きました」
瞬間。エリザベートの眉が、つりあがる。
「何じゃと、無礼者――!!」
フランシスの髪をひっつかみ、その頭を壁にたたきつけようとするエリザベート。
普段ならフランシスはその鋼の如き忠誠心をもって、抵抗することなく主の嗜虐心を満たしてやるのだが――
――今日の彼は岩のように不動、ビクともしなかった。
ただならぬものを感じたエリザベートは、即座に叫ぶ。
「ええい、衛兵! 何をしておる! この痴れ者を、今すぐに――」
「無駄です、陛下。衛兵は全員殺しました」
エリザベートの表情が、固まった。
周囲の沈黙と、何よりフランシスの澱んだ眼が、真実を物語っていた。
「おのれ……よくもヌケヌケと、この謀反人めが! そなたはラクルテル家の名誉に泥を塗ったのだ!」
よく見ると、顔に返り血のような赤い染みを付着させたフランシスは。
「私の質問にお答えください、陛下。返答次第では――」
眼をクワッと見開き、狂人の形相で、続ける。
「――貴女様を殺して、私も死にます」
此奴は本気じゃ……!
と、エリザベートは本能でそう理解した。
いくら彼女が武術の達人とはいえ、帝国最強の騎士であるフランシスをひとりで仕留めるなどできはしない。
どう返答すべきか……?
エリザベートが人類の限界に迫る明晰な頭脳をフル回転させて思考し、はじき出した答えは――
「ひひ――う、嘘に決まっておろう! そんなもの。わわわ、妾は、マスカール皇家稀代の名君、エリザベートぞ! ななな、なにゆえ、妾が父上を、こ、殺さなければ、ならぬのじゃ。ばばば、馬鹿も休み休み言わぬか――ぶ」
エリザベートの胸に深々と埋没する、血塗られし刃。
「キ……サ……マ……」
口から赤い血の滝を吐き出し、エリザベートは即座に絶命した――
彼女は生まれてこのかた、嘘をついたことがなかった。
その持って生まれた天賦の才と権力により、嘘をつく必要などなかったからだ。
そんな無敵の女王が初めてついた嘘は、実にお粗末なものだった。
あの天上天下唯我独尊、神をも恐れぬ女帝の。
眼が泳ぎ、声が震え、嘘を真実にするべくばたばたと落ち着きなく取り繕う、その醜態は。
女中の不動の覚悟とは、対極のもので。
フランシスに剣を抜かせるには――充分だった。
エリザベートの返り血で真っ赤に染まった、彼女の騎士は。
「ご安心を……我が君よ。私もすぐに同じところへ逝きます故――」
すぐさま己の首にその剣を突き立て。
血飛沫とともに己が君の上に覆いかぶさるように倒れ、その生命活動を停止した……
もしここでエリザベートが毅然とエリーヌの言葉を否定したならば、フランシスはその凶刃で逆にエリーヌを斬り殺し、やはりその場で自害していただろう。
無敗の女帝のその強さ――裏を返せば嘘をつく修羅場に恵まれなかったその境遇こそが、最期の最期で仇となったのだ。
* * *
エリザベートが死んだことで、城内は騒然としていた。
自らが死ぬまで玉座に居座るつもりだったエリザベートは、後継者についてまったく考えておらず、したがって世継ぎはいなかった。
残された臣下たちが国の行く末――否、次の最高権力者の座を巡って唾を飛ばしあいながら醜く議論している、その傍らで。
女中のエリーヌが、心の中で、密かにほくそ笑んだ。
――ごめんなさい、愛しのフランシス様。
私はあなたに、嘘をつきました。
実をいうと、エリーヌはエリザベートが先王の主治医を殺した場を目撃したわけではなかった。
ただ女中の間で耳にした噂話を、しかしベテラン女優顔負けの演技力をもって、フランシスに話したにすぎなかったのだ。
エリザベートとは対照的に、生まれながらの平民であり、弱者だったエリーヌ。
――彼女の父は征服戦争の最中に戦死。
そして体を売ってまで一家を養っていた母もまた、エリザベートが引きあげた重税によってとうとう食えなくなり、ある日パンを盗んで憲兵に殺された。
当時十歳だったエリーヌは、まだ五歳だった弟とともに家を追い出され。
しかしその弟も、真冬の厳しい路上生活には耐えられず、凍死。
独りぼっちになってしまったエリーヌは、それでも死にきれなかった。
私からすべてを奪った、あの邪智暴虐な女帝に復讐するまでは、死んでも死にきれぬ、と。
ありとあらゆる嘘をつき、他人を騙し、裏切り、利用しつくし。
とうとう給仕として城で働くことを許され、何年もの間、復讐の機会を伺っていたのだ。
エリザベートなどとは、ついてきた嘘の数がまるでちがう。
フランシスのような武骨者ひとりを騙して利用することなど、造作もないことだった。
――それから三日後。
結局エリザベートの後釜は、彼の右腕として政治を取り仕切っていた宰相が引き継いだ。
が、非凡なエリザベートとは違い、お上の言うなりになるしかない凡庸なイエスマンだった彼は、国内をひとつにまとめあげることはできず、やがて内乱が勃発。
そしてエリザベートの死から三年後、マスカール帝国は地図上から消滅した。