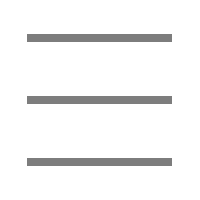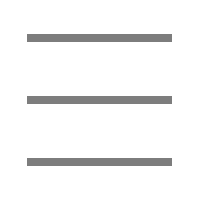おれの名は暴田堕無怒。市立世紀末高校に通う、どこにでもいる普通の高校二年生だ。
学校での成績は常時最下位、出席日数も余裕で足りなかったが、教師を説得して進級を果たした稀代の赤点王である。
「あー。最近暇だなー」
学校をサボり出して間もない頃は町に繰り出してそのへんのゴロツキをボコしたりして遊んでいたのだが、今となってはどいつもこいつも人の顔を見るなり脱兎の如く逃げ出していく。
社会の汚物どもを痛めつける時の快感は何物にも変えがたいのであるが、これでは退屈でしょうがない。
だから今日はひさびさに登校することにした。気まぐれにな。
「ヘッヘッヘ。堕〜無〜怒〜、ここで会ったが百年めだァ〜。今日こそ積年の恨みを晴らしてやるぜェ〜」
しかし、そんなひさびさの登校を阻むように、こないだボコした隣町の悪虐高校の番長・魔鬼村大凶と、ヤツの舎弟二十人が、おれの通学路で待ち伏せしていた。
ひさびさの獲物を前に、おれは舌舐めずりをする。
「おれひとりに頭数かき集めてごくろうなこったな。雑魚が百人集まろうがおれに勝てるわけなかろう」
「ウルセェェ――クソガァァァ――‼︎」
憎しみに駆られた魔鬼村は狂った猿のように吠え、部下ともども一斉におれに襲いかかった――
――百人集まろうが勝てないというのは、誇張でも何でもない。
人間離れした天性の怪力と異常なほど頑強な肉体を持つこのおれは、五歳にしてすでに近所の大型犬を殴り殺し、ついこないだは動物園を脱走して襲いかかってきた熊を締め殺しているくらいの武力の持ち主であり、こんな連中など赤子の手をひねるかのようにひねり潰すことができる。
「シネェー化物ガァ――‼︎」
魔鬼村の持った釘バットが、おれの側頭部をしばく。
「今何かしたか」
おれはヤツの釘バットを掴み、そのままバキボキべきと握り潰した‼︎
そして魔鬼村の額に手を伸ばし――デコピンをおみまいする。
たかがデコピンと侮るなかれ。
人間離れした超怪力が繰り出すそれは、プロボクサーの繰り出すストレート級を伴い――
「化物……が……」
魔鬼村の額をたたき割り、地に沈めたのであった。
「何見てるんだよ、アアン?」
いつの間にか周囲にできていた人だかりも、しかしおれが凄むと蜘蛛の子を散らすように逃げていく。
「ちっ。とんだ道草食っちまったぜ」
とりあえずやることもないので、おれはそのまま学校へ行くことにした。
* * *
「うっ……あ、暴田……くん」
久々に投稿したおれの顔を見るや否や、担任教師の顔が露骨に曇る。
「あんだよ」
おれが見返すと、担任は気まずそうに視線をそらせる。
「小物が」
すぐにどうでもよくなって、おれは忘れかけていた自分の席に着席し、机の上に足を乗っけて独りスマホでツイスターのタイムラインでも眺めている。
すぐに朝のHRの時間も終わり、古文の授業が開始される。
光ナントカいう変態が幼女をF〇〇Kしたとかいう話に多少は興味を抱いたが、不自然なまでに何も話さず、教師が無言で黒板に文字を刻むチョークの音が眠気を誘う。
ひさびさに学校来たってのに、つまんねー。
おれは退屈からくる眠気に耐えられなくなり、うたた寝していたが、変な姿勢で寝ていたため、腰痛を再発する。
ベッドで寝るか、と、おれは授業中にもかかわらず無言で起立し、保健室へと歩き出した。
国語教師がこちらをチラチラと見つけてきたが、知ったことじゃない。
赤点とろうが何だろうが武力ですべて解決する。
一応はおれのために学費を捻出している親の望みに応えるために高校だけは卒業してやるが、手段はこちらで決めさせてもらおう。
* * *
ふてぶてしく無言で侵入するおれを笑顔で迎えるのは、二十代半ばほどの、白衣姿の若い養護教諭だ。
こいつの名は江口成子。
保健室に君臨せし白衣の天使――クラスの野郎ども曰く超絶美人の養護教諭、とのことだったが、白衣の下のYシャツのボタンは第二まで外れており、そこから覗く胸の谷間にいちいち注目してしまう。
美人というより、ただのエロい女だな。
おれが抱いな江口への第一印象は、そんな感じだった。
「どうしたの? どこか具合でも悪いの?」
おれの顔を見ても物怖じせず、ただ純粋に心配そうに……いや、おれが退屈のあまり保健室に寝に来たのを見透かしているとでもいわんばかりに顔を覗きこみ、江口はそう訊ねる。
「ああ。死ぬほど眠くてな。ちとベッド借りるぜ」
「怪我、してるわね」
江口はおれの額に手を伸ばす。
ゆうに四十センチくらい身長差があるため、背伸びして手を伸ばすその姿が、何だか可愛らしく思えた。
「湿布薬を貼ってあげる。待ってて」
「いらねえよ。怪我なんて大それたもんじゃねえしな」
「ここに来たからには保健室の番人である私の言うことには従ってもらうわよ。ほら、そこに横になって」
強引ではあったが、慈母のごときその優しい眼差しにはなぜか抗いがたい力が感じられた。
「仕方ねえな」
おれは渋々とそうこぼしながらも江口の指示に従い、ベッドに横になる。
「また喧嘩でもしたの?」
悪戯っぽい笑みを浮かべてそう訊ねる江口。
「まあそんなところだ。連中のひとりが釘バットでおれの頭しばいてきやがってな」
「喧嘩なんて、だめよ。いくら暴田くんが強くても。相手はひとりとは限らないわ」
「関係ないね。おれは誰にも負けねえ」
「今はそうかもしれない。でも、もしものことがあったらどうするの」
そんなことは、考えたこともなかった。
「どうでもいいな。万一、いや億にひとつもおれが怪我したところで、あるいは――仮に路上のどこかでくたばったところで、誰も悲しまねーよ」
その言葉を聞いて、江口が何だか悲しそうな顔をした。
憐んでいるつもりか。
……どうでもいい。
おれはそのまま、言葉を続ける。
「親父は仕事、おふくろは男のことしか頭にねえし、友達なんざいねえ」
おれの言葉を聞き、江口は真剣な眼差しでおれの眼を見つめ――
そのまま無言で、おれの体を抱きしめた。
いい匂いだった。
教室の女どものようなむせ返るような香水の臭いはなく、その髪からはシャンプーの香りがほのかに漂ってくるのみ。
「――私が悲しむわ。暴田くん。だから、もう喧嘩なんか、しないで」
おれを哀れんだつもりか、と、江口の顔を覗きこんではみたが、彼女の顔は真剣そのものだった。
「あー……考えとくよ」
おれは江口の眼を直視できず、歯切れの悪い声でそう答えるしかできなかった。
保健室の天使……か。
保健室を出てから、しばらく動悸が収まらない。
クラスメイトの女どもはおれに恐れをなして近寄ってこないし、母親にすらどうでもいいと見放されていたおれにああまで接近した女は、江口が初めてだったろう。
それを抜きにしてもあいつには他の女にはない、何か――形容しがたい魅力を、持っていた。
これが……恋というやつなのだろうか?
正直恋だなんて都市伝説か何かの類か、あるいはテレビでひたすら流される恋愛映画やドラマに毒された脳みそお花畑どもの妄想の産物なのだと、勝手に思いこんでいた。
が――江口のあの女神の如き慈愛に満ちた眼ざしを思い返す度に――どういうわけか、胸が締めつけるような感覚を、覚えるのだ。
「また行こうかな……保健室」
この日を境に――おれは三年間続けてきたゴロツキ狩りをやめた。