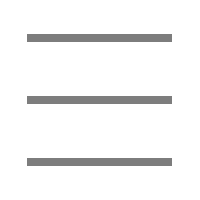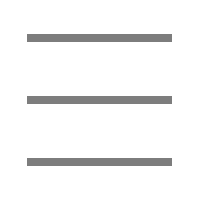ばす、と、玩具のような音をたてて銃口に備えつけられたサイレンサーの先から吐き出されたほかほかの九ミリパラベラム弾が、黒いトレンチコートを着た三十代くらいの大柄な男――そう、刺客の心臓を、正確に貫いた。すでに〈機関〉を抜けて天涯孤独の身と化しているため、死体の後処理をしてくれる〈始末班〉は来てくれない。人を殺す術は知っていても、死体を跡形もなく迅速に処理する術を、〈彼〉は知らなかった。もたもたしていれば、あの白金ヒヅルのよこした第二、第三の刺客が自分の命を狙うだろう。仕方なく彼は追手の死体をそのままにして山小屋を後にした。
彼の名は、地獄谷村正。日本を代表する巨大財閥・白金グループの裏の顔である〈白金機関〉で、かつて諜報員を務めていた男だ。彼は、白金学園大学部において高い知能と超人的な運動神経を併せ持つ万能の天才として白金機関にスカウトされ、主に秘密工作や暗殺といった暗部の仕事を任されていた。が、極めて独善的な性格と思想の持ち主で、自分の理想とする世界に不要な人間、特に破落戸や犯罪者といった連中を人間失格と称して大量に虐殺していたことが発覚。白金機関総帥・白金ヒヅル自らの手で粛清するはずだったのだが、逆に返り討ちにして逃走。二人の護衛が死に、一人が重体、そして白金ヒヅルは腕に全治二週間の傷を負い、として白金グループの闇の歴史に刻まれるに至ったのであった。
しかし裏の世界においては日本はおろか世界中にネットワークを持つ白金機関の追手から逃げ続けるのは、至難の業であった。裏切り者には死。それが機関の掟だからだ。白金ヒヅルは身内にこそ寛大だが、裏切り者に対しては無慈悲という他ない。おそらく村正が生きているかぎり、地の果てまでも永遠に追ってくるであろう。
さて、これからどうするか、と、村正は考えていた。白金機関の追手は厄介だが、おいそれと殺される自分ではない。殺されず逃げ切れるとして、どこでどうやって生きていくべきか。白金ヒヅルによる〈粛清〉から命からがら逃げ延びたため、金がない。とりあえず、大学時代の知りあいでもあたるか、と、スマートフォンを取り出そうとして、家に置き忘れてきたのを思い出した。まあいい。どのみちあのババアのことだから、盗聴していたり位置情報を掴まれる可能性は多分にある。
白金機関の動きは実に迅速で、白金グループ傘下の銀行はおろか、村正が金を利用していた他の六つの機関の預金や資産はすべて凍結されていた。
厄介なのは、警察の中にも白金機関のスパイが多数紛れこんでおり、すでに村正は過激派組織IU(イスラミック・ユニオン)のテロリストとして全国に指名手配されている。さらには白金グループが筆頭株主であるメディア、テレビや新聞、ネットなどでも大々的に手配書が掲載され、もはや村正は社会的に抹殺されたと言っても良い。金さえあれば、嘘でも何でも報道する。まったくろくでもない。この国は、あの白金ヒヅルのクソババアに乗っ取られつつある、と、村正は心の中で毒づいた。
「くそめんどくせえ」
途方に暮れた村正は、素性を偽って犯罪組織の用心棒ないし殺し屋として金を稼ぎ、裏社会での独自のつながりを作りつつ、今後の身の振り方を考えていた。白金機関は裏社会にも絶大な影響力を誇るが、髪も髭も伸ばし、指名手配書の写真とはまったく別の風貌で、名前も〈黒金日没〉という偽名を使っていたので、素性が割れることもなかった。だが、白金機関の情報網を甘く見てはならない。あくまで一時しのぎにしかならないのは、村正自身が一番よくわかっていた。
黒金日没の名が裏社会に浸透してきた頃、彼の元にある大きな仕事が舞いこんだ。依頼者は愛国党総裁にして日本国総理大臣、鷹条林太郎。総理としての顔はあくまでも表向きなもので、彼の正体は世界最大の闇組織ヘリオスの日本支部長、所謂ジャパン・ハンドラーであるのは、裏社会に精通している人間の間では常識であった。鷹条総理が持ちかけた案件とは、当時勢いを増しつつある最大野党労働党の総裁であり、次期総理の座を狙っている大沢三郎の抹殺。大沢は白金ヒヅルの忠実な懐刀であり、政権交代によって彼が総理の座に着けば、いよいよ日本は白金ヒヅルの独裁国家になる。それを危惧してのことだった(無論鷹条総理が居座る今はヘリオスの独裁国家ということになるが、白金ヒヅルの独裁に比べれば幾分ましだと村正は考えていた)。
だが、正確には村正に与えられた仕事は殺しではなく、ヘリオスの暗殺者のサポートであった。ヘリオスには腕利きの狙撃手がいるのだが、その相方が最近任務中に死んでしまい、急遽代理が必要であった、とのこと。漫画や小説の世界では狙撃手が単独でビルや茂みの中から獲物を狙うという描写が散見されるが、実際の戦場では観測手と呼ばれるサポーターと共に行動することが多い。スコープを覗きこんでいるとどうしても狙撃手の視野は狭くなるため、観測手が肉眼や双眼鏡で周囲を警戒し、情報を収集し、敵の接近を報せたり、時には排除したりすることで、狙撃手は安全かつ確実に、標的の狙撃に集中できるというわけである。また、狙撃手は長時間過酷な環境下で潜伏することもあり、疲労などによる命中精度の低下を防ぐために観測手が交代で狙撃手を務めることもある。
閑話休題。「今回の任務での働き如何では、破格の待遇でヘリオスの兵士として採用したい」――村正に仕事を持ってきたヘリオスの使いが村正の素性に気づいてなかったのか、そう言ってきた。急速に勢力を強めつつある白金機関に押され、ヘリオスのスカウトが優秀な人材を求めて裏社会を彷徨っているという噂は本当だったらしい。いずれにせよ、今回の話は村正にとってはまさに渡りに船だった。白金機関の追手から自身を守るのはもちろんのこと、あわよくば自分を殺そうとしたあの白金ヒヅルに復讐できるチャンスが、訪れるかもしれない。そう考えていた。