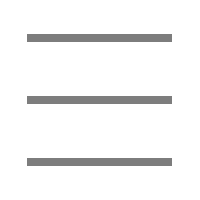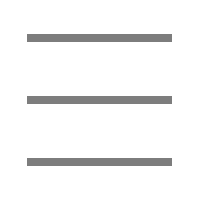村正が懲罰房で過ごしていた間に、ヘリオス日本支部のリーダーすなわち鷹条総理が〈全権委任法〉を閣議決定し、名実共に日本の最高権力者となるべく、動き出していた。憲法の制約すら無効化するこの法案は、言うなれば日本を鷹条総理の独裁国家に作り変えることであり、当然野党側は猛反発していた。
そこで鷹条総理はヘリオスの暗殺部隊を駆使し、野党議員本人やその家族を事故や病気に見せかけて抹殺するという強硬手段に出たのだが、すぐに野党議員、殊に白金ヒヅルが掌握している最大野党労働党の議員とその家族には白金機関の護衛が付き、ヘリオスの暗殺計画を悉く妨害するようになった。そこで元白金機関の村正に白羽の矢が立ったというわけだ。戦闘員として、殺し屋として極めて有能かつ白金機関の内情にも詳しい彼を、懲罰房で遊ばせておく余裕は今のヘリオスにはなかった。
村正はクローディアと組み、白金機関の護衛ごと野党議員やその家族たちを抹殺していった。無論表向きは事故ということにされていたのだが、〈全権委任法〉に反対している議員ばかりが次々と標的にされていたため、鷹条総理の暗黙のメッセージは議員たちには充分すぎるほど伝わっていた。逆らえば〈粛清〉される、と。
法律が国民のルールならば、憲法とはすなわち為政者を対象としたルールである。基本的人権や三権分立などのルールとは、すなわち為政者の暴走に歯止めをかけるための、民主主義国家にとってなくてはならない箍のようなもの。全権委任法は憲法に縛られることなく、鷹条政権に無制限の立法権を与える。つまり国会の承認を必要とせず、すべては鷹条内閣の思うがままというわけだ。無論閣僚たちは全員鷹条総理の腹心たちであり、全権委任法可決イコール独裁国家ヘリオス帝国の誕生である。だが村正は、それでも白金ヒヅルによる独裁国家白金帝国よりはましだと考えていた。
全権委任法の最終審議日を迎えると、国会の前ではふたたび数十万人規模のデモ隊が集結していた。さらには本来ヘリオスの兵隊であるはずの警官たちが、何十人もデモ隊を守るように周囲で眼を光らせていた。以前国会前でデモ活動をしていた連中に鷹条総理はロケット弾を撃ちこんで黙らせるという強硬手段に出たのだが、これでは同じ手は通用しないだろう。
「くそ。裏切り者どもが」国家保安委員会情報総局の一室で、高神が舌打ちした。
「あの警官どもは白金機関の兵隊か」 村正が訊ねた。
「いや。警察内部に潜んだスパイの仕業だろう。警察内部でも鷹条政権の独裁に反対する反乱分子はいる。連中を焚きつけ、同時にネットやメディアでも国会前デモを呼びかける。民主主義を守ろう、だと。裏で糸を引いてるやつが何を企んでるかも知らずに」
国家保安委員会情報総局、その局長といえば、ヘリオス日本支部における情報戦略の最高責任者である。得意の情報戦において劣勢なのが腹立たしいのか、高神は顔をしかめながらぼやいた。野党議員の家族は、最終審議日の一週間前には全員行方不明となっていた。おそらく村正たちによる暗殺や拉致を危惧して、白金機関がどこかに避難させたのだろう。念を押してヘリオスの工作部隊に「全権委任法に反対する抵抗勢力の議員とその家族すべてを殺す」という怪文書メールやFAXを送らせたのだが、どうやら裏目に出たようだ。
議員たちの家族は白金機関の保護下にあり、国会議事堂の外では数十万の民衆が全権委任法反対のデモを行っている。これでは抵抗勢力の議員たちが賛成票を投じることはないだろう。そして世論調査による支持率では鷹条総理率いる政権与党愛国党はわずか三パーセント、対して白金ヒヅルの労働党は四十二パーセントで圧倒的首位。次の選挙で政権交代が起こるのは火を見るよりも明らかである。全権委任法による国の掌握が失敗すれば、それはヘリオスの敗北、すなわち白金ヒヅルによる日本征服の完了を意味する。
「できれば、穏便に事を済ませたかったんだがな」高神は深いため息をついた。「日本をヒヅルの手に渡すわけにはいかん」
「仕事か。姉御」村正が、毒々しい紅の四白眼を輝かせながら口角を吊りあげた。
「おそらく全面戦争になる。覚悟を決めろ」
村正たちが国会議事堂に到着してから十数分後、鷹条政権による〈全権委任法〉の多数決が実行された。
結果は惨敗。三分の二以上の反対により、全権委任法は否決された。
「そうか。あくまで我が覇道の邪魔をするか。白金ヒヅル」
高神が無線で配備完了を報せた直後、鷹条総理は立ちあがり、叫んだ。
「鷹条君。静粛に。私語は慎みなさい」
議長が厳かな声で鷹条総理に命じた。国会においては総理大臣よりも議長の方が立場は上であり、議場の警察権も議長が握っている。たとえ総理大臣と言えども、議長の鶴のひと声で議場の外へと追放することができるのだ。
しかし、それはあくまで表向きの話。
「遊びは終わりだ。議長。狡い蝿どもの相手をしてやるのはもう飽きた。誰がこの国の支配者であるか、はっきりさせる時が来たのだ」
鷹条総理が、右腕を高く掲げた。
ぱぱぱぱぱ。
国会に似つかわしくない乾いた音が、議場全体に谺した。
公衆席、記者席、そして衛視や速記者、愛国党の議員までもが、一斉に隠し持った拳銃を抜き、引金を引いたのである。