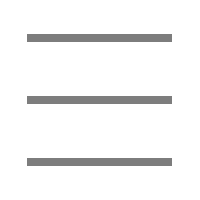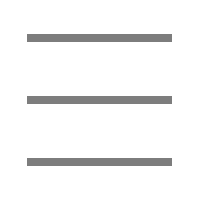「ふん。お前がクロガネか。裏社会では多少有名みたいだが、今回の任務はヘリオスの今後を左右する重要な戦いだ。失敗は許されない。……くそ。何だって高神隊長はこんな馬の骨に、私の背中を……」
秘密結社ヘリオスの精鋭部隊ラブアンドピースの一員であり、凄腕の狙撃手として裏社会では〈スナイパー・クロウ〉の名で知られている、クローディア・クロウの第一印象は、最悪だった。まるでどこぞのお姫様か令嬢のように、あれこれと村正に指図してくる。この女、観測手を奴隷か何かと勘違いしてるんじゃないか。
村正が露骨に不服そうな態度でいると、クローディアはあたかも自分が村正の命運を握っているかのように高圧的に接してきた。
「今回の任務に失敗すれば、お前はヘリオスの始末屋に消されるだろう。お前にはふたつの道しかない。この任務を成功させ、ヘリオスの殺し屋として生きるか。あるいは任務に失敗し、殺されるかだ。ヘリオスの内部機密を知った者は、たとえ〈協力者〉であろうと生かしてはおけない。それが掟だからな。任務を成功させたいなら、私の言う通りに動け。余計なことは考えるな。わかったか鳥頭」
なぜ彼女の前の〈相棒〉が死んだのか、村正にはわかった気がした。
相手は白金ヒヅルの懐刀にして白金機関の幹部。想定通りそう安々と殺されてくれるはずもなく、任務は難航した。大沢の側には常にまったく隙を見せぬ護衛が何人かいた。村正には、彼らがヒヅル直属の特殊部隊〈白金の剣〉のメンバーだとわかった。特に厄介なのは――
御菩薩池政志。世界各地の紛争地で長年戦闘に参加していた百戦錬磨の傭兵で、現在は白金ヒヅルに忠誠を誓った〈白金の剣〉の副隊長を務める男。
「ありゃ手強いぞ。クロちゃん。狙撃する隙なんて与えてくれるとは思えねえ」
「何だ、その呼び方は。お前は自分の立場が」
突発的に飛んできたクローディアの鋭いパンチを、村正は掌で受け止めた。
「な」村正の抵抗が意外だったのか、クローディアは眼を見開き、声を洩らした。
村正はそのままクローディアの腕を捻りあげ、彼女の背後をとり、耳元で囁くように低い声でこう言った。
「いいかよく聞け。じゃじゃ馬。俺は誰の下僕にもならねえ。ただ金の対価として仕事をする。それだけだ。相手はプロ中のプロだ。……が、俺はヤツについてお前よりもよく知っている。俺がこの任務を、成功に導いてやる。しくじれば俺だけじゃなく、手前も死ぬってことを忘れるんじゃねえ」
力では敵わないと悟ったのか、観念したようにクローディアの腕の力が抜けていった。
「ふん。そこまで大口叩くなら、聞かせてもらおうじゃないか。やつを仕留める具体的な作戦を」
クローディアの問いに、村正は間髪入れずに応える。
「白金機関のSPは、スーツの下に特製の防弾チョッキを着込んでる。肉の盾どころじゃねえ。カーボンナノチューブの盾だ。ライフル弾でも殺せねえ。あのセンチュリーの防弾ガラスの厚さは二十センチ。対物ライフルでもぶち抜くのは無理だ。狙撃で殺るのは無理がある。俺についてこい」
「おい。どうする気だ」
「将を射んと欲すれば先ず馬から、だ」
どんなに警備を強化しようと、人間とは二十四時間厳戒態勢で生活することは難しい。鍛え抜かれた歴戦の兵士ならまだしも、標的は戦争を知らぬ素人。そんな暮らしを続けていれば、おそらく十日も経たぬうちに気が狂ってしまうだろう。御菩薩池政志のようなベテランがついていようが、彼が二十四時間くっついて守るわけにはいかないのである。
そして戦で勝利するために何より大切なのは情報。元白金機関の村正は、大沢が無類の女好きで、妾を七人も持っており、時々狂ったように妾宅を泊まり歩いているのを知っていた。
「そんなことは我々ヘリオスとて百も承知だ。問題は、どうやって大沢を抹殺するかだろう」クローディアが鋭い眼で村正を睨みつけ、詰った。
「焦るんじゃねえよ。クーロちゃん。いいから俺に任せとけ」村正の笑みは、勝ちを確信したように自信に満ちていた。
大沢とつながりを持つ人間は政界問わずたくさんいるが、そのうちのひとりにアイドルプロデューサーとして有名な胴元愛一郎がいる。彼の裏の顔は売春の元締めで、顧客リストには大物政治家や暴力団幹部など錚々たるメンバーが名を連ねている。大沢三郎もその中のひとりであり、彼の妾のひとりは胴元が斡旋したアイドルユニットKGB48のナンバー1アイドル、粂煌梨である。実は村正は、彼女と面識があった。
粂煌梨は金銭欲と承認欲求の塊のような女だった。邪悪な欲求を持つ権力者に取り入り、利用することに長けていた。今から六年ほど前、村正が白金学園高等部の三年生だった頃、彼女は一年生だった。煌梨は入学式で首席生として挨拶するほとの優等生であったが、当時の村正は彼女と同じく首席入学して以来ずっと学年一位の成績保持者であり、野球部ではエースで四番という漫画キャラのようなカリスマ的存在であった。煌梨はそんな村正に惹かれたのか、ふたりは次第に恋人同士のように同じ時間を共有するようになっていった。が、優等生の仮面の下に巧妙に隠された煌梨の黒い本性に、村正は何となく気づいていた。後に煌梨は白金学園高等部の校長を身体で買収し、成績を改竄させていたことが発覚。校長もろとも学園を追い出された。
それ以降、村正は煌梨と会うこともなく、後に彼女がアイドルとしてスカウトされたことを知った。人気投票で同じグループの菊地鞠那と一、二を争う関係であったが、しばらくして菊地が突然他のユニットに移籍させられるという事件があり、これは煌梨がプロデューサーを〈買収〉したのだな、と、村正は悟った。
粂煌梨は金や権力を得るためには手段を選ばぬ女だ。そこで村正は、彼女を大沢の攻略に利用しようと企んだ。
「あれー。村正先輩じゃないですかあ。久しぶりですねえ。今何やってるんですか」
都内の一等地にある、成人したての女の独り暮らしとしては不釣りあいなほど豪華な高層マンションの一室に、村正は招かれた。大沢に買ってもらった、と、煌梨はあたかも自ら勝ちとった戦利品よろしく得意げに言った。
世界を裏から支配する秘密結社の殺し屋、と言ったところで頭のおかしい中二病患者だと思われるに違いないので、村正は前職の白金商事の社員であると嘯いた。
「へー。そうなんですね。エリートじゃないですか。いひひ」
もはや村正が自分の本性を知っていると悟っているのか、煌梨は特に取り繕おうともせず、下品に笑った。
「で、その白金商事のエリートさんが、何の用です? 今日はこれからパパと会うんだから、手短にお願いしますね」
煌梨は値踏みするような眼で、村正を見て言った。彼女のその双眸の奥底にある澱みは、高校時代の比ではなかった。欲に濁った、腐敗しきった溝池の如き眼だった。