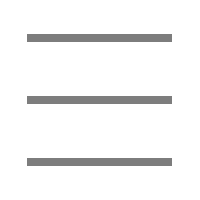
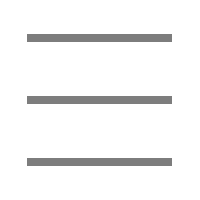
こんばんは、Eninことお好みPです。
昨日ニコニコ動画とYouTubeで新曲を公開しました。
最初は眠くなるような曲調を目指してたんですが、色々いじってるうちに何か「オフトゥンは偉大なり」みたいな曲になりましたw
メインボーカルは一部界隈で「オペラの女王」と呼ばれている京町セイカさん。
C6くらいの高音でもすごくきれいに出るのでモーツァルトの魔笛なんかも余裕で歌ってくれます。
今回は初のデュエット作品ということで相方を誰にするかでかなり迷った末に弦巻マキちゃんに決まりました。
彼女の声はデフォルトだとけっこう柔らかくて優しめの歌やコーラス、ハモリに向いてると思う。
セイカさんもマキちゃんも今月24日にSynthesizer V2版が発売予定で新しいボーカルスタイルが追加されるらしいので楽しみ。
オーケストラの編曲は実のところこれが3曲めで、ようやく制作のフローが定まりつつある。
バンド音楽だとベースから打ちこむことが多いんだけど、オーケストラの場合はストリングス、その中でもチェロとコントラバスから打ちこむと何かやりやすい気がする。
低音のリズム隊で全体の展開を決めて(コード進行もほぼ一緒に考える)、そのリズムに合わせてギターとかバイオリンとかを乗せていく。そんな感じ。
木管と金管はストリングスのメロディを補強したり置き換えたり対位法で対となる旋律を書いたりで、ストリングスの譜面を参考に合わせて作っていく。
ドラム、シンバルとかティンパニとかの打楽器系は最後に音を補強するように打ちこむことが多いですね。
ぼくにDTMを仕込んでくれた友人はドラムから作ると言ってたし、これが正解だと言う気はさらさらないのでそんなやり方もあるんだなあ、くらいに思っといてください。
音源はオーケストラ音源としては定番の BBC Symphony Orchestra (Core)で、今年の初めくらいのセールで買いました。
BBCSOは無料の Discover 版もあってこれだけでも結構使えるし、音源がほぼ無いReaperからDTMを始める人にはオススメのオーケストラ音源なんだけど、Core版の方が当然奏法のバリエーションも音質も良い。
オーケストラ音源については比較対象がUVI Orchestra SuiteやMiroslav Philharmonikくらいしかないけど、実際使ってみて思ったのはBBCSOはベタ打ちしてExpressionで雑にメリハリつけるくらいの調整でもけっこう生演奏感が出るということ。
MVについては最初は背景も全部描くつもりだったんですが、途中でモチベが尽きてフリー映像素材を突っ込む作戦に急遽変更。
でもこっちの方が動きも変化も出せて良いんじゃないか、背景を描くにしてもキャラとは分離した方が良いという知見を得られたので結果オーライw
そんなこんな!
これまでニコニコ動画だけで活動してきたけど、最近YouTubeチャンネルも作りました。
作品が気に入りましたらチャンネル登録&高評価よろしくお願いします!
ニコニコの方がボカロというか音声合成ソフト関連のイベントもあるし、全曲チェッカーとかいうイカレた(褒め言葉)リスナーたちもいたりで無名の新米ボカロPが発掘されやすい環境なんじゃないか、と漠然と思っていたんだけど、やっぱりせっかく生み出した曲は一人でも多くのリスナーに聴いてもらいたい。
YouTubeではあんまりボカロ関連の動画見たりしないし今後もニコニコがメインなのは変わらないと思うけど、少し前にニコニコに投稿された夢ノ結晶公式の動画が全然伸びてなかったのが気になっていた。
そもそもニコニコとYouTubeじゃリスナーの層が全然違うのでは、と。
Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY×浜渦正志/停止線上の障壁(バリア)
夢ノ結晶といえばちょっと前にぼくの脳を焼いたアニメ Ave Mujicaも手掛けるブシロードのバンドリプロジェクトがリリースする本格派AI歌唱ライブラリシリーズ。
ROSEさんはぼくもちょっと前にお迎えしてこないだSV2にアプデしたばかりなんだけど、その公式がプロ作曲家に依頼して制作されたMVが3桁再生止まりという事実に衝撃を受けた。
ぼくのMVと変わらん。
浜渦正志さんといえばFF等の音楽も手掛ける大御所の作曲家で、MVのクオリティもたぶん動画制作のプロが手掛けたもので非常にクオリティが高い。
なお同じ動画がYouTubeでも投稿されててそっちはこの記事を書いてる2025年7月6日現在で50万再生(笑)。
ニコニコの方が後から投稿されてるからYouTubeの方が伸びるのは当然なんだけど、それにしても1000倍差は開きすぎw
いわゆるバンドリーマーたちはたぶんYouTubeを観る層が多いんじゃないだろうか。
自分の音楽がYouTubeで伸びるかはわからないが、試してみたい。
てなわけで、今後はニコニコとYouTubeの二刀流で行きます。
そんなこんな!
どうも、eninです。
キラハピ2025に投稿したバミちゃんこと青春系ソングボイス双葉湊音ちゃんの新曲「Bluesky」がニコ動で初の4桁再生となりました。
ニコニコのみならずXでもいいね数が過去最多となってて嬉しみ。
やはり人はキラキラした曲を求めるのか。
Twitter改めXのスパムやゾンビ、ブロックの改悪やヘイトを煽る「対戦型SNS」としての運営方針、投稿したイラストをAIの餌にする規約の改悪などなど、色々と嫌気が差してアカウントを抹消してから早1年。
かつての青い鳥を求めて移住した新SNS・Blueskyはまさに新天地だった。
インプ稼ぎのゾンビもいないし、ツイートに群がるスパムもいない。
フォローしてもいないインフルエンサーのくだらないデマやヘイト煽りのツイートが流れてくることもない。
ブロックすれば当然ぼくの投稿は敵からは見えなくなる。
ユーザーは気の赴くままに日常を呟く。
古き良き黎明期のTwitterのようだ。
とはいえ、BlueskyはXほどメジャーではないし、ユーザー数もXの未だ10分の1以下。
作品の宣伝や情報収集という面においてはXの方が優れていると認めざるをえない。
そんなわけでXにアカウントを新しく作り直しはしたものの、ぼくの魂は未だBlueskyと共にある。
居心地がいいのはやっぱりBlueskyなんだよな。
そんな新天地SNS・Blueskyの(非)公式ソングを作ってみたいという構想はBlueskyに移住した1年前くらいからあったものの、なかなか歌詞や曲のアイデアが降りてこなかった。
DTMを始めてもう4年近く経つというのに、未だに己の音楽性がわからない。
しかし迷子のままでも進みたい。
双葉湊音ちゃんの曲はこれが3曲めだけど、どれも青春系ソングボイスの名に相応しいメジャーコードを多用した明るくエネルギッシュなロック曲となっています。
デビュー曲「君の青春物語」
2曲め「小さな勇気」
今回コメントで好評だったギターソロは Ample Guitar TC のリフモードで作った。
Ample Guitar は音も素晴らしいんだけど、リフモードとかストラマーモードとかの打ち込み補助機能も搭載しててとても使い勝手が良い。
ギターの打ち込みってピアノロールだけで完結しようとするとすごい大変。
ギター弾ける人は弾いた方がたぶん手っ取り早いw
ロックやメタルを作りたいけどギターやベースの打ち込みとか大変すぎて無理……Ample Sound製品はそんなDTMerの救世主ともいえる音源だ。
ギターやベースを禄に弾いたことのないぼくですらリスナーを魅了するサウンドを生み出せたのだから間違いない。
そんなこんな!
Synthesizer V Studio 2(SV2)がリリースされてから3カ月ほど経つ。
最初のSV2ライブラリは期間限定無料アプデで手に入れた宮舞モカちゃんだったけど、夢ノ結晶ROSEもSV2にアプデすることにした。
夢ノ結晶POPYとROSEのSythesizer V1版を持ってるユーザー向けにSV2ライブラリのアプデコードがブシロードのオンラインストアで販売されている。
なおSV2にアプデしなくてもSV1の互換ライブラリというものを使えばSV2でROSE SV1を使うことはできる。
Synthesizer Vのライブラリは1でも十分表現力お化けだけど、SV2にすればさらに化ける。
で、表題の件。
ブシロードのオンラインストアでアプデコードを入手したまでは良かったのだが、SV2でのアプデ認証を試みたところ……
製品が無効とは……?
ROSE SV1はDLSiteで購入した正規のライブラリだし、割れ製品なんて当然使ってない。
ブシロードのサイトから落とした「はじめにお読みください」ファイルには詳細な手順は記されておらず、AHSのサイトへのリンクが貼ってあるだけ。
よくある質問に「Synthesizer V Studio 2 ProのアップグレードコードをDreamtonicsアカウントに登録することができません」て項目があったけどROSE SV1はSV2にすでにインストールされているしでワケがわからん。
シリアルはメールからコピペしてるし、メモ帳にコピペして変なスペースとかが混入してないか確認してるので打ち間違えとかも起りようがない。
そもそも適当なコード入力したらライブラリの選択画面すら出ずに弾かれる。
色々試した結果、アプグレのシリアル登録ルートは2通りあることが判明した。
アプグレ用のシリアルコードの登録手順がどこにも書いてないので「製品を追加」ボタンから登録してたんだけど、ROSE SV1の「バージョン2へアップグレード」ボタンからでもいけることが判明。
さっきは「5/1」とか表示されてた数字が「1/1」に変化してて初めて日付じゃなくてライセンス数だったんじゃないかと気づく。
5という数字に心当たりがなさすぎるのでてっきり日付だとばかり(
5000円弱で5つのライブラリをアプデできるとか太っ腹すぎる。
どうせ弾かれるだろうと思ってスクショ撮ってなかったんだけど、「アップグレードを適用」ボタンを押したらあっさり通った。
Dreamtonicsのサイトから問い合わせようかと思ったんだけど何かAHSのサイトに飛ばされるし、そもそもブシロードのストアで買ったコードの登録なのにAHSのサポートが対応するのかもよくわからん。
SV2、歌声合成の技術は素晴らしいのにこういう認証周りがちょっと残念。
あとROSE SV2の期限切れてた体験版が残ってたから途中でアンインストールしたんだけど、期限切れのライブラリが邪魔してた可能性も考えられなくもない。
トライアンドエラーの果てに晴れてSV2に進化したROSEさんだけど、認証が通らなかった原因は結局わからずじまい。
サポートもなしにアプデを成功させられる人どのくらいいるんだろう……
そんなこんな!
Reaperって日本国内だとけっこうマイナーなDAWらしい。
Sleep Freaksの調査によると0.6%くらいなんだとか。
シンプル、軽い、安い、スクリプトで拡張し放題で良いDAWだと思うんだけど、日本だとあんまり流行ってないのはCubaseとかみたいに日本語の情報があんまり出回ってないからじゃないだろうか。
というわけで、素晴らしきReaper使いが日本で少しでも増えるよう、備忘録をシリーズ化することにした。
ぼくの知り得た情報をちょくちょくここでシェアしていこうと思い、「Reaper」って専用カテゴリも新設した。
さて、表題の機能について。
ギターとかオーケストラの音源って演奏切り替え用のキースイッチが鍵盤に割り当てられてて実際の楽器に近いリアルかつ多様な奏法を再現できるようになってるんだけど、どの鍵盤に何の機能が仕込んであるか覚えるのってけっこう大変。
なので、ピアノロール上に表示できたら便利だと思ってたんだけど、Reaperでそれを実現する方法を発見した。
どうやるかだけど、まずピアノロール上に表示する文字をまとめたTXTファイルを用意する。
たとえばぼくのよく使うAmple Metal Eclipseのキースイッチだと
30 Tap
29 HamOPI
28 Legato
27 SlideIO
26 PMute
25 NHarm
24 Sustain
という記載になる。
左の数字はC-1=0から始まる連番になってて、たとえばC1だと24、C2だと36、といったように増えていく。
格納場所は特にいじってなければ
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\REAPER\MIDINoteNames
とかになってると思うので、そこにTXTファイルを保存。
ピアノロールの左の鍵盤の上あたりを右クリックして……
File > Note/CC names > Load note/CC names from file > Choose file
と選んでいくとTXTファイルが出てくるので開くと鍵盤にキースイッチ名が出てくる。
鍵盤上にだけ表示されててノートの上に出てこない時はここが無効になってるはずなので有効にする。
TXTファイルベースで自由にいじれるので他の音源のキースイッチも全部表示できる。
ドラム音源もこの通り。
どこでどんな音が鳴るか一目瞭然で打ちこみやすいね。