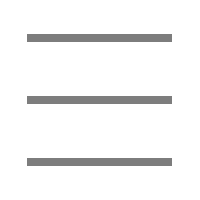
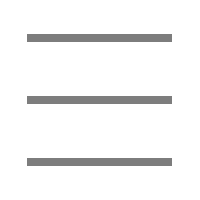
Universal Audio といえば最近タガが外れたようにセール連発してて話題のプラグインメーカーで、ぼくはまだDTM界隈に来て2年そこそこのルーキーだから良く知らなかったんだけど、どうやら名機をたくさん作ってきた老舗のオーディオ機器メーカーらしい。
UAの作った名機は色んなメーカーがエミュレーションプラグインを作ってて、元々プロ向けのお高い本家プラグインが8割とか9割引きという気が触れたようなセールで趣味DTMerの手に入るようになれば話題にもなるというもの。
ぼくもこのビッグウェーブに乗って LA-2A や 1176 を買って使ってみた。
実機エミュレーション系のプラグインは PA の Shadow hills とか bx_console くらいしか使ったことなかったけど、DAW付属のデジタルコンプだと音が潰れて劣化するレベルのリダクションをかけても音が全然破綻しなくて感動した。
シンプルなプラグインの割にはプリセットが豊富で、ボーカルとかギターとかドラムとかにかける時はどういう設定にすれば良いのか勉強にもなる良プラグインだと思った。
そんな良いことずくしでおまけにセールで安く手に入るコスパ最強クラスの UADも、実はひとつだけ問題がある。
プラグインをインストールする時に UA Connect って管理アプリを使うんだけど、こいつがプラグイン起動時にオンライン認証も行うらしく、常駐させておかないといけない。
オフラインだとこんなことになる。
いや、わかるよ。
悪いのは有料の商品をパクる割れ厨とかいう泥棒どもで、メーカーは身を守るために商品を鍵つきのケースに入れたり対策しないといけないもんね。
スタバとかでDTMすることもあるぼくみたいな移動型クリエイターにとっては常時オンライン認証求められるのはめんどくさいんだけど、それだけなら CeVIO も同じだし、まあ我慢できる。
でもね、UADくん。
作業中にいきなり「アプデしろ」って画面に割りこんでくるのはやめてくれ。
創作がノリにノッてる時に邪魔されるのは気に食わない。
DAWを起動してなくても絵を描いてる時にまで画面に割りこんでくるもんだからそのまま衝動的にアンインストールしてしまった。
UA Connect の自動アプデを手動に切り替える方法ないか探してみたけど今のところないっぽい。
気にしない人は気にしないんだろうけど、あんまりユーザビリティが良いとは言えない気がする。
せめて手動アプデできるようにしてほしい。
ネット上じゃ UAD を絶賛する記事ばかりでこういう情報なかったから書いてみました。
UA Connect 問題が解消するまではもう UAD のプラグインは使うことはないと思う。
Melda や PA (Plugin Alliance)は常駐アプリも常時オンライン認証も求めてこないしプラグインの質もいいので、ぼくにはうってつけ。
今度ともよろしく。
以前に参加したコンピ「終末コンピレーション『終末branchout』」でお世話になった夕立P主催のコンピに再び参加させていただいた。
その名も……
終末×紀行コンピ『終末Travelers』
2024年春のM3とニコニコ超会議に出品しててそのタイミングで宣伝記事を書くべきだったんだけど、まあ、コロナで死んでたので……
最近BOOTHとBandcampでの通信販売も開始したとのことでこの場で宣伝です。
Bandcampの方では各トラックを個別に試聴、購入もできるので気に入った楽曲だけほしい! という方もぜひぜひ。
CD版は1000円、DL版は500円となります。
歌モノとインスト(楽器のみ)が半々くらいでジャンルもバラバラで、前作同様バラエティ豊かな、良い意味でカオスなアルバムとなっております。
ぼくは6番目の「亡き世界へのレクイエム」という曲で参加してます。
どんな曲かは実際に曲を聴いてほしいんですが、前回のコンピ曲同様めちゃくちゃ暗いですw
ボーカルは前回と同じCeVIOのゆかりさん。
何というか彼女の歌声は暗い曲との親和性が高い気がする。
最近2.0版のソングボイスがリリースされて、ベタ打ちでもあまり追加の調声が要らなくなったというか、より滑らかに人間らしく歌うようになったように思う。
伴奏は前回はほぼシンセのみの近未来的なものでしたが、今回はパイプオルガンのみ。
楽器をひとつに絞った弾き語りスタイルの曲は初挑戦でしたが、試みは成功したといっても差し支えないです。
根拠は完成曲をぼくが自然とヘビロテしたからです。
第一のリスナーであるぼくがヘビロテしたくなるかどうかは、楽曲の完成度を示すひとつの指標だと思っている。
終末コンピについてですが、終末Recordsというブランドを出していて今後も定期的にアルバムを出していく方針のようなので、ぼくもまた参加すると思います。
お楽しみに。
MMDとは「MikuMikuDance」の略で、ネット上に無数に配布されてるキャラクターを手軽に動かしてダンス動画とかが作れる素晴らしいツールです。
で、ぼくのような一次創作フリークスはオリジナルキャラのモデルを作って動かしてみたいと考えるのですが、3Dモデルを1から作るのはなかなかハードルが高い。
そこでVROIDの出番です。
VROIDはネトゲのキャラクリのような手軽さでオリジナルキャラを作れる素晴らしいツールです。
開発元はお絵描き投稿サイトで有名なあのPIXIVだそう。
で、ここで作ったモデルをどうMMDに導入するかですが、まずここからVRMというファイル形式で書き出しします。
MMDはVRMファイルに対応してないので、ここからPMXというMMDで使えるファイル形式に変換する必要があります。
VRM2PmxConverter という有志が開発したこれまた素晴らしいツールが存在するのでこれを使わせていただきます。
モデルを読み込ませて「Convert to PMX」ボタンを押すだけ。
自分でモデリングしてみるとわかるのですが、本来ならモデルを作ったらそれで終りではなくボーンとか剛体とかの難解な設定が必要なのですが、そのへんの設定も全部やってくれます。素晴らしいね。
ただぼくのモデルの場合、こんな感じに髪の色がファンキーなことになってしまうようなので、これを修正します。
色々情報を漁って試行錯誤しましたが、テクスチャを直接いじるのが一番てっとり早そうです。
何か適当な画像編集ソフトでテクスチャを開きます。
一番左の本来の髪の色でこんな感じにコピペして全部塗りつぶします。
無事解決。やったぜ。
ちなみにこれはPMXエディタというMMD用のPMXモデルを編集するためのツールで、モデルの見栄えとかボーンや剛体の設定とか細かく色々いじれます。
あとはMMDにPMXモデルを読み込ませて、ネット上にある膨大な宝の山(有志の制作したステージやモーションなど)から好きなものを拝借して読み込ませるだけ。
これだけで自キャラのモデルが可愛らしく踊ってくれます。
うーん。素晴らしい。
ちなみにVROIDでオリキャラモデルを作る場合、アクセサリーの自作が難しかったり(できなくはない)、顔立ちが似たような感じになりやすいので、こだわりの強いクリエイターは3Dモデリングソフトを使って改造したりします。
やり方は色々ありますが、ぼくの場合はVROIDからVRMファイルで書き出してそれをメタセコイアという3Dモデリングソフトにインポートして改造します。
メタセコイアは国産の3DモデリングソフトでMMDユーザーに使用者が多く、モデリングに特化しているためBlenderなどの統合3D制作ソフトに比べて操作がシンプルで使いやすいです。
また、追加プラグインなしにVRMやPMDファイルの読み書きに対応してる点も魅力です。
ぼくのアバターのフジミちゃんは鼻立ちが割とくっきりしてて、VROIDの設定を色々いじって再現を試みたのですが結局満足のいく仕上がりには至らず。
編集が完了したらまたVRMファイルとして書き出して、あとはそれを上記の方法でPMXに変換するだけです。
いやはや、たくさんの有志の方々が神ツールを無償公開してくれるおかげで本来なら年単位で制作するような3D動画も簡単に作れてしまう。
素晴らしい時代になったもんです。
異変に気づいたのは6日ほど前。先週の火曜日だ。
何となく身体が重く、寒気がする。喉には違和感。
ああ。これはとうとう、ぼくもババを引いてしまったか。
体温計の数字は37.3℃、しかしこんなもんでは済まないだろうことは容易に予測できた。
なぜならその数日前に家族がコロナと診断されたにも関わらず出社してきたバイオテロリストがいたからだ。
会社に問い合わせたところ、コロナでも医師の証明があれば傷病手当金をもらえるとのことだったので、早く直すためにも医療機関を受診し、検査したところ案の定の陽性。
これを書いてる4/29現在、もう熱は下がり、ブログ記事が書けるくらいには病状は落ち着いたが、まだちょっと声を出しただけで無限に咳が止まらなくなるくらいには喉が死んでいる。
ボイトレやカラオケはしばらくできないだろう。
最初の3日間は40度近い高熱が続き、弱毒化したとはいえ10年くらい前にかかったインフルよりも強烈だった気がする。
ぼくがコロナに罹ったのはたぶんこれが初。
今までも無症状だっただけで実は感染していたのかもしれないが。
しかし最近Xのアカウントを抹消したせいもあって世情に疎くなっており、今は5日分のコロナの治療薬が3割負担でかなりの高額になっていることを知らなかった。
コロナの特効薬、ゾコーバ錠。
お値段びっくり1粒7400円。
全部じゃないよ、1粒7400円。
今回処方されたのは7粒だったので総額は5万円強。
ミドルレンジのスマホが買えちゃう。
3割負担だと16000円ちょいだけど、それでも1回の処方でこれはなかなかしんどい。
そのあまりのお値段に、薬屋が処方前に所持金の確認までしてくる始末。
たぶん払えずに断る人とかいるんだろうな……
最近のコロナは肉体だけでなく預金残高にまで深刻なダメージを与えに来るらしい。
凶悪すぎる。
【追記】
そういえばコロナ陽性だったにもかかわらず味覚障害にはなってない。
おかげで今日もUberで注文したビッグマックが美味しかった。
以前の記事で両声類シンガーに憧れて女子声を出す練習を始めた、という話をした。
色んな両声類の人の講座を参考にあれこれ試しながら毎日ちょっとずつ練習を続けて早4カ月。
今ではこのくらいの声は出るようになった。
ボイチェンの類は一切使ってない。
裏声をベースにしてるせいか、ちょっと幼い感じ。
理想とは少し方向性が違うけど、まずは自分の出しやすい女子声を伸ばした方が良いらしいのでたぶんこの路線でいくと思う。
声自体出るようになってもまだ話したり歌ったりすると崩れちゃう。
壁があるのはたぶんこの先じゃないかな。
美少女シンガーソングライターへの道は高く険しい……
ぼくの地声はかなり低い方だけど、それでも数カ月練習すればこのくらいの声は出るようになるみたいです。
人によっては1日で出せたり、逆に1年くらいかかったりと習得期間は本当に人それぞれだそう。
以下は参考にした講座(一部)。
・【女声講座】元ダミ声が教えるゼロから始める女声!【両声類】